ピグマリオン効果とは?ゴーレム効果との違い、ビジネスでの活用方法と注意点

ピグマリオン効果という心理学から成る考え方が、ビジネスシーン、とくに人材育成の側面で注目されています。
人材育成において、このピグマリオン効果を利用することで、部下の成果は向上することがわかっています。ただし、ピグマリオン効果を活用するためには、上司や指導者側がピグマリオン効果の内容をより深く理解しておく必要があります。
本記事では、ピグマリオン効果とは?という基本的な内容に加え、その他の心理的効果とどのような違いがあるのか、ビジネスにおいて有効に活用するためのポイントを解説します。
目次
ピグマリオン効果とは?
ピグマリオン効果とは、他者からの期待によって成績が向上する現象を意味する教育心理学の用語です。「ローゼンタール効果」や「教師期待効果」とも呼ばれ、アメリカの教育心理学者ロバート・ローゼンタール氏によって提唱されました。
このように、ピグマリオン効果はもともと、教師の期待によって起こる児童の心理行動に対する知見でした。現在では、上司と部下の立場に置き換えられ、成果をあげるための心理効果としてビジネスでも活用されるようになりました。
ピグマリオン効果の言葉の由来
ピグマリオン効果の「ピグマリオン」は、ギリシャ神話に登場するピグマリオン王に由来します。
ピグマリオン王は、自分で彫刻した理想の女性像に恋をし、神々の力でその女性像が実在する女性になるように願いました。神々は願いを受け入れ、女性像はガラテアという人間の女性となり、ピグマリオン王と結ばれることになります。
ピグマリオン効果は、この相手(女性像)に期待をしたことが、良い結果につながったというストーリーをもとに名づけられました。
心理学におけるピグマリオン効果の実験
ロバート・ローゼンタール氏は、教育現場で下記のような実験を行い、ピグマリオン効果という心理現象を発見しました。
通常の知能テストを「学習能力予測テスト」と名づけ、小学校6年生の児童に実施。教師には、今後成績が伸びる児童を予測するためのテストであると説明したうえで、<テストの結果から選定した今後成績が伸びる児童>の名簿を渡しました。しかし、実のところ名簿に記載されていたのは、テストの結果とはまったく関係のない、無作為に選ばれた児童でした。にもかかわらず、名簿に記載された児童は、その後実際に成績が向上したのです。
この実験から、教師の高い期待が無意識のうちに教師の行動に影響を与え、それが生徒の学習意欲や成果にポジティブな影響を与えたことが示されました。つまり、教師が児童に「成績が向上する」と期待したことで、児童側は「期待されている」と意識し、成績が向上したというロジックです。
この実験は、ピグマリオン効果の存在を証明した代表的な研究として知られています。そして、ビジネスにおける上司と部下の関係でも同じことが言えます。ピグマリオン効果は、教育現場の実験から始まり、今やビジネスシーン、医療、スポーツ、恋愛、家族関係など、様々な分野で応用されている心理的効果なのです。
ピグマリオン効果と比較される3つの心理学的効果
心理学の分野には、ピグマリオン効果とは逆の心理を促す心理効果や、ピグマリオン効果に類似する心理効果も存在します。それぞれの違いを理解し、ピグマリオン効果の本質を捉えていきましょう。
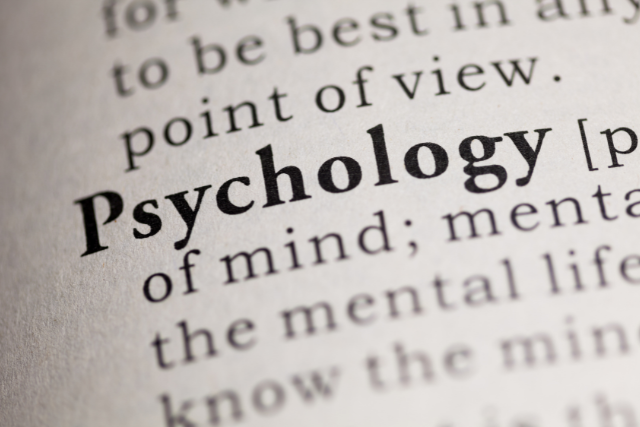
【ゴーレム効果】 ネガティブな期待の影響
ゴーレム効果とは、他者からの低い期待が、パフォーマンスの低下を引き起こす心理効果です。ピグマリオン効果と同様に、ロバート・ローゼンタール氏によって提唱されました。
ゴーレム効果とピグマリオン効果の違い
ピグマリオン効果は肯定的な期待がポジティブな成果をもたらすのに対し、ゴーレム効果は否定的な期待がネガティブな結果を生む点で、ピグマリオン効果と逆の現象と言えます。
ゴーレム効果の検証実験では、成績の良い児童を集めたクラスと成績の悪い児童を集めたクラスが作られ、成績の良いクラスの教師には成績が悪いクラスだと、成績の悪いクラスの教師には成績の良いクラスだと伝えました。すると、もともと成績が良かったクラスでは成績が下がり、もともと成績が悪かったクラスでは成績が上がるという結果になりました。
期待されていないことが児童に伝わることでネガティブな連鎖を生み出してしまうのがゴーレム効果であり、ピグマリオン効果とは対照的な現象であると示されたのです。
【ハロー効果】 第一印象の影響力
ハロー効果とは、一部の特性によって、対象の評価や印象を歪める現象です。アメリカの心理学者エドワード・ソーンダイク氏によって提唱されました。
例えば、「偏差値の高い大学を卒業しているから大きな成果を出せるだろう」「テレビで紹介されていたから美味しいお店だろう」といった思い込みを指します。目立つ特徴があることで、対象が本来の価値以上に優れたものだと錯覚してしまうのです。
ハロー効果とピグマリオン効果の違い
ピグマリオン効果は、期待を通じて相手の行動そのものが変わる現象です。一方で、ハロー効果は評価する側の認識にのみ影響を与え、評価者の内側のみで完結する現象であることから、ピグマリオン効果とは異なります。
【ホーソン効果】 観察が行動を変える
ホーソン効果とは、周囲から注目・期待されることで、成果を出そうと力を発揮する現象です。アメリカのホーソン工場において、労働者の作業効率を上げるための調査のなかで発見されました。
例えば、表彰を受けた社員が、その後も周囲の期待に応えようと努力をすることで、高い成果を出し続けられるというものです。
ホーソン効果とピグマリオン効果の違い
ピグマリオン効果と似ていますが、ピグマリオン効果とホーソン効果では「誰に期待されるのか」という点に注目すると違いが分かります。ピグマリオン効果は“特定の他社からの期待”でパフォーマンスが向上するのに対し、ホーソン効果は“不特定多数からの注目”によってパフォーマンスが左右されるということです。
ビジネスシーンにおけるピグマリオン効果の活用方法
教育心理学の分野における心理効果であるピグマリオン効果ですが、ビジネスシーンで大きな効果を発揮します。本章では、具体的な活用方法を解説し、職場での人材育成や組織パフォーマンスの向上につなげるポイントを紹介します。
- 能力に応じた目標を設定する
- 肯定的な言葉でモチベーションを維持する
- 部下に裁量を与える
- 適切な期待値を設定する
- 目標達成に向けたプロセスを評価する
- 公平な人事評価を行う
- ロールモデルを活用する
ここからは、上記の具体例をみていきましょう。新入社員や部下の教育・指導では特に役立つテクニックです。
能力に応じた目標を設定する
部下1人ひとりの能力に応じた目標を設定しなければ、適切な重みで期待をかけることができません。
低すぎる目標では「自分は期待されていない」と感じてしまい、成果の向上は見込めません。反対に、高すぎる目標では「自分には無理だ」と不安に感じ、モチベーションが下がったり、本来のパフォーマンスを発揮できなかったりします。
上司は、部下がモチベーションを維持しつつ、乗り越えられるハードルの高さを見極める必要があります。
肯定的な言葉でモチベーションを維持する
肯定的な言葉を使って褒めることで、部下のモチベーション維持につながります。
部下の指導において、出来ていないことや失敗したことに対して、叱咤激励することが多いのではないでしょうか。しかし、「もっと頑張れ」「このままだと目標は達成できない」といわれると、「自分は期待されていないんだ」と不安になり、ゴーレム効果によってネガティブな連鎖が生じてしまいます。
本人のやる気がなければ、成果をあげるための努力もできません。部下のモチベーションを下げないために、「あなたならできる」「ここが良かった」「これができたらさらに伸びる」といった肯定的な言葉を選んで、具体的に伝えましょう。ピグマリオン効果によって部下の自信が高まり、成果の向上が期待できます。
部下に裁量を与える
部下に適度な権限を委譲することで、部下は上司からの期待を感じることができます。
肯定的な言葉を使って、部下に期待していることを伝えても、部下の行動をすべてチェックして、逐一指示を飛ばせば、「口では期待していると言っているが、本心では期待していないのでは?」と感じられるでしょう。
ピグマリオン効果を利用するためには、上司や指導者側が相手に期待しているということを意識してもらわなければなりません。期待するというのは、本人の能力や努力を信じることでもあります。任せられる業務をしっかりと任せることで、期待している・信頼していることを行動で示すことができるのです。
よって、上司には、部下のやりたいように仕事をさせつつ、目標達成に向けて方向性をコントロールするスキルが求められます。
適切な期待値を設定する
適切な目標設定と同様に、上司から部下への適切な期待値の設定も重要です。
上司が部下に対して期待することで、ピグマリオン効果が生まれますが、過度な期待をかけすぎるとプレッシャーが大きくなり、「自分では期待に応えられない」とネガティブな感情につながってしまいます。「こんなに期待しているのになぜできないのか」と責めてしまうと、部下の自己肯定感は下がり、自立性や自主性が失われかねません。
そのため上司は、部下の性質・性格やプライベートの状況、仕事のレベル、能力に合わせた期待値を見定める必要があります。上司の価値観や理想を押し付けるのではなく、部下の状況を理解し、共感したうえで、部下が自信を持てる程度の期待を示しましょう。
目標達成に向けたプロセスを評価する
部下の頑張りを評価するときは、成果のみならず目標達成に向けたプロセスにも目を向けましょう。
適度なハードルを設けても、人によっては十分な成果に結びつかないこともあります。成果が出せなかったからといって上司が落胆したり責めたりすると、部下は自信を失ってしまい、次のステップに進めません。そこで、実際にどのように仕事を進めたのかを評価し、継続して期待を抱いていることを示すのです。
上司は、目標達成のためのアイデアや努力する姿勢、スキルの向上など具体的なポイントに着目し、解像度を上げて評価を行いましょう。部下が上司からの期待を引き続き感じられ、自信を失わないことが大切です。
公平な人事評価を行う
部下が期待に応えられて成果を出したら、しっかり評価に反映することも重要です。
上司の期待に応えても、正当な評価につながらないのであれば、当然ながら社員のモチベーションは下がってしまいます。期待されても意味がないと感じられてしまえば、上司との信頼関係は破綻し、ピグマリオン効果も失われてしまいます。
公平な評価基準を設け、成果や目標達成に向けた努力が評価されることで、引き続き自身の仕事を前向きに遂行してくれることでしょう。
ロールモデルを活用する
職場で成功している先輩社員をロールモデルとして紹介することも、ピグマリオン効果を促進する方法の一つです。「彼のように成長できる」「同じ成功が手に届く」といった期待感を生み出すことで、社員は自分の可能性を信じられるようになります。
例えば、新入社員向けの研修で、優秀な先輩社員が「自分も最初は未経験だったが、努力で成果を上げられるようになった」といった体験談を共有することで、成長の道筋をイメージさせることができます。
ピグマリオン効果を活用したマネジメントの注意点
ピグマリオン効果は、適切に活用しないと逆効果になる場合があります。本章では、ピグマリオン効果の欠点を明確にすることで、実際にマネジメントをする際に注意すべきポイントを解説します。
- 過度な期待はプレッシャーになり得る
- 期待がネガティブに伝わるリスクがある
- 個人差を考慮しないと逆効果になる
- 結果に依存しすぎない
過度な期待はプレッシャーになり得る
ピグマリオン効果を活用する際に最も注意すべき点は、期待の度合いです。過剰な期待は、相手にプレッシャーを与え、逆にパフォーマンスを低下させる「ゴーレム効果」を引き起こす可能性があります。
例えば、上司が部下に「君なら絶対にトップの売上を達成できる!私だけじゃないよ、チームメンバーや社長だって君に期待しているんだからな」と過剰な期待を押し付けた場合、部下はストレスを感じ、逆に成果を出しづらくなることがあります。
このような場合、前章の【ビジネスシーンにおけるピグマリオン効果の活用方法】における「適切な期待値を設定する」ことを意識することで解消できます。また、「肯定的な言葉でモチベーションを維持する」ことで、プレッシャーを軽減できるでしょう。
期待がネガティブに伝わる場合がある
期待を伝える際のコミュニケーション方法によっては、相手がその意図をネガティブに受け取る可能性があります。期待が「監視」や「干渉」として感じられる場合、信頼関係が損なわれるきっかけになってしまうでしょう。
例えば、上司が「もっと努力すればできるはずだ」と言った場合、相手にとっては「今の努力では足りない」と否定されたように感じられることがあります。
このような場合、前章の【ビジネスシーンにおけるピグマリオン効果の活用方法】における「肯定的な言葉でモチベーションを維持する」ことと「部下に裁量を与える」ことで、信頼関係の上で仕事の連携ができるようになるでしょう。
個人差を考慮しないと逆効果になる
ピグマリオン効果はすべての人に同じように効果を発揮するわけではありません。人によっては、他者の期待が重荷になりやすいタイプや、自己効力感が低い場合があり、期待がプレッシャーにしかならないこともあります。また、組織は同じ実力や経験値を持った社員だけが集まるわけではないため、チームメンバー全員に同じ期待のかけ方をすると、周りを意識しすぎてモチベーションを維持できない社員も出てきてしまうでしょう。
このような場合、前章の【ビジネスシーンにおけるピグマリオン効果の活用方法】における「能力に応じた目標を設定する」ことと、「公平な人事評価を行う」ことで個人の能力を最大化できます。
結果に依存しすぎない
ピグマリオン効果を期待するあまり、短期的な成果だけを評価する姿勢になると、長期的な信頼関係を損ねる可能性があります。
例えば、成果が期待通りに出なかった場合に、「期待外れだ」と感じさせる態度をとると、相手の自己効力感が著しく低下してしまいます。
このような場合、結果(成果)だけではなく、努力や成長のプロセスにも目を向け、成果が伴わなくても適切なフィードバックを与えることが重要です。前章の【ビジネスシーンにおけるピグマリオン効果の活用方法】における「目標達成に向けたプロセスを評価する」ことや「ロールモデルを活用する」ことで長期的な目線での人材育成につながるでしょう。
ピグマリオン効果を使えば組織は活性化する

社員が働きやすく、成長できる職場環境は、オフィス環境や勤務体系といった目に見える部分だけではなく、心理的な要素も大きく関わっています。上司が部下に期待している、信頼しているという気持ちを示すだけでも、部下の成果が大きく飛躍することもあります。
ピグマリオン効果を利用して、人材育成を行うときは、部下のモチベーションや自信が失われないよう、適度な期待値と目標を設定できる上司側のスキルが重要になってきます。たとえ部下が失敗をしても、失敗を責めたり一方的に指示・命令したりせず、成果を焦らず、部下が自ら答えを出すまで見守る忍耐力も必要です。
ぜひ今回お伝えしたピグマリオン効果を意識して、社員との向き合い方を再検討してみましょう。






