コアコンピタンスとは?意味、条件、評価軸、経営戦略への見極め、企業事例を紹介

競争社会が激化する現代において、企業が競合優位性を獲得し、今後も成長を続けるためには「コアコンピタンス」が欠かせません。
本記事では、コアコンピタンスがどのような概念なのか解説します。また、コアコンピタンスを確立するための流れやコアコンピタンス戦略に成功した企業を紹介します。自社のコアコンピタンスの確立のためにお役立てください。
目次
コアコンピタンスとは?
コアコンピタンスとは、企業が競合他社には真似できない形で価値を創出し、持続的な競争優位を築くための中核的な能力や技術を指します。英語の“core”は和訳すると「中核」を意味し、“competence”は「能力」「資産」という意味があります。コアコンピタンスは、この2つが組み合わさった用語であり、事業を成長させるための経営戦略の1つとして注目を集めている概念なのです。
この概念は、経営学者ゲイリー・ハメル(Gary Hamel)とC.K.プラハラード(C.K. Prahalad)が1990年に発表した論文「The Core Competence of the Corporation(Harvard Business Review)」で初めて体系的に提唱されました。日本語としては、日本経済新聞出版社より1995年に「コア・コンピタンス経営 -大競争時代を勝ち抜く戦略-」として出版されています。
企業環境が急速に変化する中、価格競争だけでは持続的な成長が難しい現代において、自社ならではの独自性=コアコンピタンスは、長期的な競争優位性の源泉として重要視されています。
特に、人材育成や組織文化、技術開発といった内部資源の強化こそが、外的変化に強い企業体質をつくる鍵となります。
コアコンピタンスの3つの条件
コアコンピタンスの定義として、3つの条件を兼ね備えている必要があります。
- 真似されない能力
- 喜ばれる能力
- 求められる能力
これらの能力を満たしている場合、自社のコアコンピタンスとして認められます。
真似されない能力
真似されない能力とは、つまり「他社にはない独自性」です。他社が簡単に真似できるようであれば、企業ならではの強みとはいえません。コアコンピタンスを確立するためには、他社を圧倒するほどの独自性を持っている必要があります。
喜ばれる能力
喜ばれる能力とは、つまり「顧客からの必要性」です。真似されない能力があっても、その能力が顧客に利益をもたらさなければ、売り上げには繋がらず、自社の利益も生み出しません。能力を用いて、他社の商品やサービスにはない機能や付加価値を提供できる必要があります。
求められる能力
求められる能力は、つまり「市場から求められる応用性」です。企業を取り巻く環境は常に変化しているため、技術力を異なる製品やサービスに応用できなければ、企業は市場において競争力を持てません。コアコンピタンスを確立するためには、幅広く応用できる能力である必要があります。

ケイパビリティとの違い
コアコンピタンスと同様に、経営戦略における企業の中核的な能力を意味するビジネス用語に、「ケイパビリティ」があります。ケイパビリティは、1992年に戦略コンサルティングのパイオニアであるBCGのメンバーによって提唱されました。
コアコンピタンスとケイパビリティは、どちらも企業の強みとなる能力を意味する用語ですが、「技術力」か「組織力」という点で異なります。コアコンピタンスがバリューチェーン上の他社と差別化できる特定の技術力を指すのに対し、ケイパビリティはバリューチェーン全体に及ぶ組織力を指します。
例えば、コアコンピタンスとしては「ホンダのエンジン技術」「ソニーの小型化技術」が挙げられます。対してケイパビリティの例は、組織全体の「研究開発力」「マーケティング力」「経営管理力」などが該当します。
コアコンピタンスとケイパビリティの関係性比較
| コアコンピタンス | ケイパビリティ | |
| 定義 | 競争優位をもたらす中核的な能力 | 組織が業務を遂行するための実行力 |
| 特徴 | 模範困難、他製品展開可能、顧客価値の源泉 | 日常業務の遂行を支える運用面での能力 |
| 範囲 | 一部の重要な能力(中核) | 広範な業務全般 |
| 影響 | 企業の中長期的な成長戦略に直結 | 短~中期の効率性や成果に影響 |
| 例 | ホンダのエンジン技術(後述) ソニーの小型化技術(後述) トヨタの生産方式(後述) | 研究開発力 マーケティング力 営業力 経営管理力 |
企業の中には数多くのケイパビリティが存在します。その中でも、特に独自性が高く、他社では真似できず、かつ顧客に明確な価値を提供できるものが、「コアコンピタンス」として特定されます。
ちなみに、組織ではなく個人の能力にフォーカスされる場合は、「コンピテンシー」という用語が使われます。
コアコンピタンス経営の重要性

コアコンピタンスが経営戦略において重視されるようになっている背景には、企業を取り巻く環境の変化が激化していることにあります。
ここでは、企業の核となる能力を活かした経営の重要性についてお伝えします。
競争優位性の獲得が期待できる
従来、経営戦略を策定するときの仮説は、過去と現在のデータを基にしてきました。しかし、常に変化を続ける現代において、過去と今だけをみていても、将来の競争優位性を獲得できるかは不透明です。過剰な現実主義では、現在わかる範囲に留まる分析になってしまいます。
この現実主義の問題を解決するのが、コアコンピタンスです。コアコンピタンスとなる能力は、変化に強く、将来的にも強い競争優位性を保ち続けることができます。さらに、企業の核となる能力を確立するなかで、企業全体にノウハウが蓄積され、環境の変化にも対応できるようになるのです。
外部環境に左右されにくい組織を作れる
近年、経営戦略に従来主流であった外部環境を変えて問題を解決する「アウトサイド・イン」の視点に加え、内部環境を活かして問題の解決を計る「インサイド・アウト」の視点を取り入れる動きがあります。
インサイド・アウトの発想では、組織の内部環境、つまりコアコンピタンスを重視することになります。内部環境を重視することで、外部環境である市場環境の変化に左右されにくい能力を持つ組織を作ることができるのです。
ただし、内部環境だけをみていては、市場環境の変化に対応できないこともあります。外部環境を考慮しつつ、内部環境であるコアコンピタンスを確立する必要があることには留意が必要です。
コアコンピタンス経営で注意すべきリスク
一方で、コアコンピタンスを重視しすぎた経営にはリスクやデメリットも考えられます。以下に記す項目も頭の片隅に置いておくことで、バランスの取れた経営判断を下すことができるでしょう。
過去の成功体験に依存しすぎるリスク
「強み」に固執しすぎると、市場環境の変化に対応できず、変革のタイミングを逃す恐れがあります。
新しい分野への挑戦が難しくなる
既存の中核能力に集中しすぎると、多様性や新規事業への感度が低下するリスクもあります。
定義や認識のズレが社内で生まれやすい
抽象的な概念であるがゆえに、部門ごとに異なる理解をされてしまい、意思決定にズレが生じるリスクも存在します。
模倣されるリスクを完全に排除できない
競合が自社の強みを分析・模倣してくる可能性は常に存在し、持続的な強化と進化が不可欠です。
コアコンピタンスは、一度定義すれば終わりというものではなく、「市場環境や技術革新に応じて常に進化させるべき“生きた経営資源”」です。
その本質を正しく理解し、組織全体に浸透させることで、企業は“他社にはない価値”を持ち続けることができるのです。
自社のコアコンピタンスを評価する5つの視点

中には、「自社にコアコンピタンスの3つの条件を満たすような技術や能力がない」と感じる企業もあるでしょう。しかし、企業の持つ能力を評価する視点と照らし合わせることで、コアコンピタンスとなりうる能力を見極めることができます。
プラハラード氏の著書「コア・コンピタンス経営」によると、コアコンピタンスを見極めるための視点には下記の5つがあるとしています。
- 模倣可能性
- 移動可能性
- 代替可能性
- 希少性
- 耐久性
自社のコアコンピタンスの確立に向け、今後磨き上げるべき能力を見つけましょう。
模倣可能性
模倣可能性は、他社が簡単に真似できる可能性があるかという視点です。
例えば、長期的なデータや経験がなければ実現できない技術は、競合他社が参入してきても模倣できない可能性が高いといえます。市場を独占するような、他社が模倣しにくい能力・他社を圧倒するレベルの能力であれば、模倣可能性が低く、コアコンピタンスとしての質は高いと評価できるでしょう。
移動可能性
移動可能性は、複数の製品や多方面の分野に応用できる可能性があるかという視点です。
例えば、幅広い製品に搭載できる機能や異なる業界で活用できるシステムなどは、移動可能性が高いため、競合優位性を獲得できます。移動可能性が高い能力は、社会のニーズに合わせて新しい製品・サービスを提供し続けられるため、コアコンピタンスとしての評価が高くなります。
代替可能性
代替可能性は、技術や製品を異なる技術に置き換えられる可能性があるかという視点です。
独自性があり、汎用性がある技術であっても、他の技術を用いれば同様の結果が得られるとなれば、市場を独占するようなコアコンピタンスにはなれません。他には代えがたい能力であれば、コアコンピタンスとしての評価は高まります。
希少性
希少性は、技術や能力が珍しいか、希少価値があるかという視点です。
模倣可能性・代替可能性の視点をクリアしていれば、希少性も持ち合わせているのが一般的です。模倣可能性・代替可能性・希少性のすべてが揃っていれば、市場において圧倒的といえるコアコンピタンスと判断できるでしょう。
耐久性
耐久性は、競争優位性を長く保つことができるかという視点です。耐久性が高いほど、企業を取り巻く環境の変化に強く、時代が変わっても強みを保持し続けられます。
ただし、変化が激しい時代において、コアコンピタンスを再発見する必要があるケースは増えています。複数の製品やサービスに組み込みながら、ビジネスを維持できる能力であればコアコンピタンスとしての評価は高まります。
【3ステップ】コアコンピタンスを見極めるためのプロセス

続いて、自社の持つ能力を5つの視点と照らし合わせ、コアコンピタンスを絞り込むときのプロセスをみてみましょう。
- 自社の強み・弱みの分析
- 自社の強みの評価
- コアコンピタンスとなる強みの絞り込み
流れとしてはそれほど難しいものではありませんが、導き出した強みからコアコンピタンスを確立するところに時間がかかります。
1.自社の強み・弱みの分析
まずは現状の分析です。自社の強み・弱みをピックアップし整理します。 強み・弱みの分析は、ブレインストリーミング・VRIO分析・SWOT分析・GAP分析・3C分析が有効です。1度の分析に終わらせず、手法を変えつつ複数回行うことで、正確に自社のコアコンピタンスとなりうる能力を導き出せます。
2.自社の強みの評価
強みに対しては、前項でお伝えした模倣可能性・移動可能性・代替可能性・希少性・耐久性という5つの視点の評価を行います。併せて、真似されない能力・喜ばれる能力・求められる能力に当てはまるのか、という確認も行います。強みの評価も、繰り返し行って精度を高めましょう。
3.コアコンピタンスとなる強みの絞り込み
最後に、評価を元に、コアコンピタンスとなる強みを絞り込みます。定義付けるコアコンピタンスによって、経営方針や経営戦略といった未来を作る意思決定に大きな影響を与えます。企業の中核となる能力なので、容易に変わるものではないため、経営陣と担当部署が慎重に議論しましょう。
コアコンピタンス戦略のポイント
コアコンピタンスを活用した戦略を取り入れるときは、下記の2点について意識しておく必要があります。
- 明確なビジョンを策定する
- 個人と企業の進化のための努力を続ける
1つずつ確認しましょう。
明確なビジョンを策定する
コアコンピタンスを見極める前に、企業が「何を目標としているのか」「将来的にどうなりたいのか」というビジョンは明確にしておきたいところです。自社のコアコンピタンスを絞り込む際に、ビジョンが明確になっていれば、実現に必要な技術や能力を判断しやすくなります。
企業としてのビジョンが明確でない場合、企業と社員の間で方向性にズレが生じたり、真のコアコンピタンスを見極められなかったりする可能性があります。
個人と企業の進化のための努力を続ける
社員の個人の能力を開発することによって、1人ひとりのパフォーマンスが向上し、企業としての成長に繋がります。企業としても、技術開発や人材開発への投資や新しい市場の開拓など、個人と企業が進化し続けるための施策が求められます。
真のコアコンピタンスを発見できても、他社に真似されたり代替できる技術が開発されたりすることがあるでしょう。競争優位性を確立できるコアコンピタンスであっても、将来的な可能性を考慮し進化を止めない取り組みが必要です。
コアコンピタンス経営を実現する企業事例
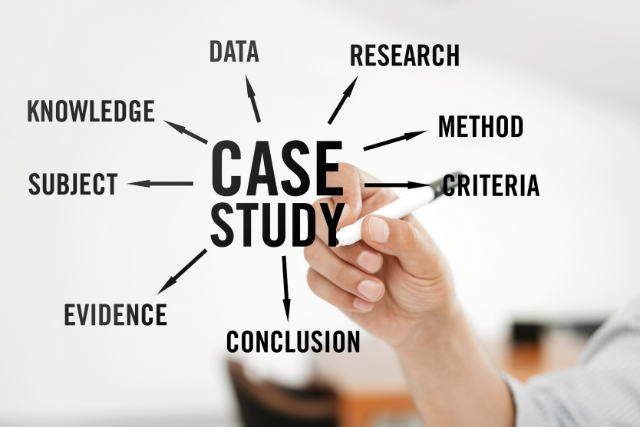
最後は、コアコンピタンス経営に成功した日本企業と海外企業の事例をみてみましょう。いずれもグローバルな市場において競合優位性を獲得しています。
富士フイルム株式会社
富士フイルム株式会社のコアコンピタンスは、「マイクロレベルでの精密な技術」と「コラーゲン生成技術」です。
かつての富士フイルムは、カラーフィルムの製造販売や写真の現像を事業基盤としていました。しかし、IT技術の進化により、大きく経営転換を計らざるを得ない状況に陥ります。
そこで乗り出したのが、医療分野や高機能材料分野への参入です。フィルムの製造に求められる「マイクロレベルでの精密な技術」と、フィルムに必要な高品質・高純度な「コラーゲン生成技術」を駆使し、一気に医療・美容分野での地位を獲得しました。ライバルだった世界的フィルムメーカーのコダックが経営破綻するなか、同時期の富士フィルムは売上高を更新する高い成果を出し、特定の技術力による事業の多角化を実現しています。
本田技研工業株式会社
本田技研工業株式会社、通称ホンダのコアコンピタンスは「エンジンの製造技術」です。
1960~1970年にかけて、日本でもアメリカでも排気ガスによる公害への対策が求められるようになっていました。特に1970年のアメリカでは大気浄化法改正法が成立。同法は、CO・炭化水素濃度を10分の1にするという非常に厳しい内容でした。
他のメーカーが基準のクリアは難しいと主張する中、ホンダはほぼ全てのリソースを注ぎ込み、新型エンジン「CVCC」を開発。アメリカの環境保護局の規定もクリアします。その後、車だけでなく芝刈り機や除雪機、航空機にも用いられ、エンジン製造技術への評価を確立しました。
ソニーグループ株式会社
ソニーグループ株式会社のコアコンピタンスは、「小型化技術」です。
1970年代当時、携帯する音楽プレイヤーといえば大きなラジカセで、携帯用としては大きすぎる・重すぎるため、気軽に外で音楽を楽しむことはできませんでした。そこでソニーは、徹底して小型化・軽量化・薄型化に取り組みます。
そして1979年ついに、ステレオカセットプレーヤーの「ウォークマン」の1号機が誕生します。片手で持てるサイズの携帯用音楽プレイヤーは、外で音楽を楽しむという新たなライフスタイルを確立しました。その後、ソニーはカメラやテレビといった電子機器の小型化にも次々と取り組んでいくことになります。
株式会社セブン&アイ・ホールディングス
株式会社セブン&アイ・ホールディングスのコアコンピタンスは、「巨大ネットワーク」です。
セブン&アイ・ホールディングスは、コンビニ・総合スーパー・レストランといった広範囲な業態と店舗網を持っています。国内で22,000店以上、世界では85,000店以上の店舗数を誇ります。
この莫大なネットワークを駆使し、店舗にATMを設置することで金融サービスを展開。24時間ATMが利用できることから、消費者には便利な生活を提供しつつ、手数料を収益とする新たなビジネスモデルを確立しました。
トヨタ自動車株式会社
世界のトヨタのコアコンピタンスは、「トヨタ生産方式」と呼ばれる無駄のない製品の生産・販売方法にあります。
トヨタ生産方式の強みは、必要なものを・必要なときに・必要な分だけ作る「ジャストインタイム」という生産システム、生産ラインに人を加えた「ニンベン」と呼ばれる自”働”化システムです。
不要なものは生産しないため無駄がなく、安定した品質を実現しつつ、最小限の在庫で管理コストを抑えられます。また、機械で自動化された生産ラインではトラブルが起きたら生産を止めて人が原因究明に当たり不良品を作らない仕組みを実現しました。
単純な考え方にもみえますが、無駄が発生しない材料の調達・供給は経験と技術力が欠かせないため、競合他社が取り入れることができず、世界トップの自動車メーカーとしての地位を確立しました。
ナイキ
世界的なアパレルスポーツメーカーのナイキのコアコンピタンスは、「ブランド力」と「マーチャンダイジング(顧客に商品を購入してもらうための作戦)」です。
ナイキの主力商品といえばスニーカーですが、このスニーカーは製造技術や品質においては他社と大きな差はありません。しかし、ナイキはブランド力とマーチャンダイジングで他社の追随を許さない価値を提供しています。
有名なところでは、史上最高のバスケットボール選手と名高いマイケル・ジョーダンを起用した宣伝でしょう。マイケル・ジョーダンにNBAで当時禁止されていた赤色のシューズを履かせ、罰金はナイキが負担しつづけ、消費者からの厚い支持を作り出しました。
ここまで共有した各事例に共通するのは、単なるスキルや設備ではなく、「企業の哲学」や「文化」レベルまで落とし込まれた能力であることです。コアコンピタンスは「見えない資産」でもあり、社内で共有・強化・発展させていくプロセスが非常に重要なのです。
成功企業の事例を通して見えてくるのは、他社にない価値を「一貫性」と「継続性」で磨き続けることの重要性です。貴社の中にも、まだ言語化されていないコアコンピタンスが眠っているかもしれません。定義し、育み、経営戦略に組み込むことが、次の成長フェーズへのカギとなるでしょう。
自社のコアコンピタンスを磨き上げよう!
競争社会を生き抜くためには、競合優位性を獲得できるコアコンピタンスが必要です。国内外問わず成功している企業には、何かその企業ならではの強みが存在します。
今、自社のコアコンピタンスがはっきりしないという場合は、今ある強みの中から、経営ビジョンにマッチするものを絞り込み、これから磨き上げることでコアコンピタンスを確立できます。ただし、コアコンピタンスの確立には時間がかかるため、長期的なプランを策定し、不足している要素や視点の獲得を目指しましょう。






