新卒採用・中途採用の進め方&成功させるためのポイントまとめ
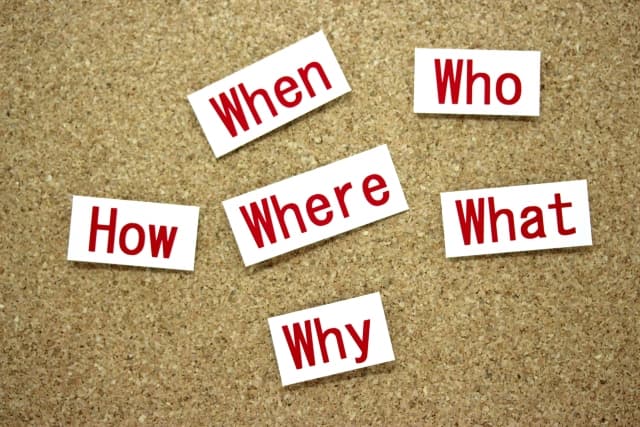
企業の運営において、人材戦略は最重要ともいえる課題です。とくに、現役世代が減少し、人手不足が進んでいることから、人材確保に頭を抱えている企業も多いでしょう。新卒採用と中途採用のどちらに力を入れたらいいのか、迷っている企業もあるのではないでしょうか。
そこで、今回は新卒採用と中途採用の進め方や、その違いを解説します。採用を成功させるために実践したいポイントも確認しましょう。
目次
新卒採用と中途採用の違い

まずは、2つの採用方法の違いを簡単に確認しましょう。
新卒採用では、社会人経験がない学生を対象に採用を行います。現在、新卒採用は経団連によって大まかな採用時期が決められているため、応募者を集めやすく、大量採用も狙えます。ただし、成長後に期待して、業務も社会人としてのマナーもゼロから教育していく必要があります。
中途採用は、すでに社会人経験や業務経験がある転職者を対象に採用を行います。職種や経験、スキルなどの条件を設定し、不定期に採用を行うため、対象者が限定され、応募者が集まりにくい傾向があります。
<新卒採用と中途採用の違い>
| 新卒採用 | 中途採用 | |
| 採用の目的 | ・若手労働力の確保 ・組織の活性化 ・企業文化の継承 | ・知識やメソッドの獲得 ・欠員補充 |
| 採用の対象者 | 社会人未経験者 | 社会人経験者 |
| 採用の基準 | 将来性 | 戦力性 |
| 採用活動の時期 | 一括採用(定期採用) ※通年採用に移行予定 | 不定期採用 |
| 採用活動の期間 | 6〜16ヶ月 | 1人あたり1〜2ヶ月 |
| 応募者の集めやすさ | 比較的容易 ※一括採用の場合 | 難しい |
それでは、どちらの採用方法が自社に向いているのか判断できるよう、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
新卒採用に関する基礎知識

新卒採用では、応募を集めやすい特性がありますが、採用が簡単なわけではありません。日本商工会議所によると、2018年度に採用できなかったり、採用人数が足りなかったりした中小企業は7割近くに上ります。
新卒採用の持つ特性を確認し、効果的な採用活動を行いましょう。
経団連の就活ルールは?
新卒採用でまず確認したいポイントが、経団連(日本経済団体連合会)が設定している「就活ルール」に従うか否かです。就活ルールとは、就職活動が学生の学業や生活を妨害してしまわないよう、経団連が企業に対して遵守を要請している方針を指します。採用スケジュールやインターン採用の禁止などが定められています。
ただし、就活ルールに応じなくても罰則はないため、早期採用を行う企業が多い現状もあります。そのため、経団連の就活ルールの存在意義が疑問視され、すでに廃止が決定しました。2021年以降に入社する学生には経団連の就活ルールは適用されません。一方で、ルール作りを引き継いだ政府は、スケジュール変更による混乱を避けるため、2022年までは就活ルールを継続する旨を発表しています。
就活ルールが廃止されたあとは、新卒採用のメリット・デメリットや、採用活動の進め方が変わるため、動向には注視が必要です。
新卒採用のメリット・デメリット
つづいて、現行の就活ルールにおける、新卒採用のメリットとデメリットを詳しく紹介します。新卒採用を始めるか迷っている企業は必見です。
メリット①組織の人員バランスがとれる
新卒採用を行うことで、若手を組織に取り入れることが可能です。中途採用ばかり行っていると、組織の平均年齢が高くなる傾向があり、企業を長期的に存続させるために必要な次世代の人材が不足してしまいます。新卒者の採用は、将来的なコア人材の採用として非常に価値あるものといえるでしょう。また、煩雑な事務作業を若手に任せることで、先輩社員の業務効率がアップし、企業の生産性の向上にもつながります。
メリット②企業文化がしっかり継承できる
中途採用で獲得できる人材は、他社と比較したり、自分のやり方に固執したりと自社の色に染まりにくい傾向があります。しかし、新卒者は社会人として白紙の状態です。そのため、自社が自社であるための文化やマインドをそのままインプットすることができ、自社らしさを引き継ぐ人材とすることができます。新卒者の愛社精神や忠誠心を育てることができれば、人材の定着率向上も見込めます。
メリット③組織が活性化する
同世代や似た思考を持つ人材が集まる環境で仕事をしていると、思考や価値観が固定化されたり、企業自体の変化がなくなったりと、企業成長にマイナスの要素が出てきます。しかし、フレッシュな新卒者が入社することで、新しい価値観やアイデアの創出、議論の発生、業務の見直しが起こり、組織に活気が出ます。時代に取り残されないためにも、企業にとって組織の活発化は新卒採用の大きなメリットです。
デメリット①戦力になるまで時間とコストがかかる
新卒者は社会人として真っ新なため、ゼロからすべて教育する必要があり、戦力として働けるようになるまで時間がかかります。また、新卒採用の採用期間はインターンを含めると1年以上、さらに研修期間が半年から1年程度必要となるため、人材やコストも必要です。プロセスが多いため、お金も時間もかけて、十分に準備する必要があります。
デメリット②選考をやり直せない
多くの就活生は、就活ルールに沿って就職活動を行っているため、タイミングを逃すとやり直すことは困難です。一度採用のタイミングを逃すと、優秀な新卒者は他社に採用されてしまい、思うような人材を確保できない可能性もあります。
新卒採用で重視したい採用基準
新卒採用のデメリットをカバーするためには、効果的に採用活動を実施し、結果を出さなければなりません。ここでは、日経連(日本経済団体連合会)が2018年に発表した、新卒採用を行った企業が重視したポイントのTOP5を紹介します。採用時に持ち合わせておきたいポテンシャルとして、選考時の参考としてください。
①コミュニケーション力
②主体性
③協調性
④チャレンジ精神
⑤誠実さ
なかでも、コミュニケーション力を重視している企業は8割を超えており、新卒採用ではぜひ選考に取り入れたい要素となるでしょう。
新卒採用のスケジュールと進め方
それでは、新卒採用のスケジュールと進め方を詳しく確認しましょう。現在、新卒採用は長期化しており、通年で採用活動を行う必要があります。競合他社と人材の争奪戦となっており、早期にインターンシップを始めて、次年度の採用に備える企業も増えています。
<新卒採用のスケジュール>
| | 5月 | ー | 採用計画の作成 |
| 6月 | 2月 | インターンシップの実施 | |
| 3月 | 広報解禁 ・採用情報の公開 ・会社説明会の開催 ・エントリーの受付 | |
| 6月 | 選考活動の解禁 | |
| 10月 | 内定出しの解禁 二次募集の開始 | |
※2020年9月時点
採用計画の作成
新卒採用では、長期的な視点で計画的に採用活動を進めることが重要です。新卒採用を成功させるためには、詳細な採用計画を作成しなければなりません。採用計画では、採用活動にかかわる方針やルールを事細かに定めます。最低限盛り込みたい項目は、下記のとおりです。
・採用スケジュール
採用活動や準備について、細かくスケジューリングします。まずは、ゴールを定めるところから始めましょう。
・採用体制
採用担当者や面接官の選定を行いましょう。欲しい人材を獲得できるかどうかは、採用担当者・面接官の応募者への対応にかかっています。応募者と信頼関係を築くために必要な知識や対応について研修を実施しましょう。採用にかかわる社員が、ほかの業務と兼任する場合は、フォローアップ体制を整えることも重要です。
・求める人物像
求める人物像の明確化は、採用活動にとってもっとも重要な課題です。新卒者にスキルや経験は求めにくいため、求人を行う職種ごとに採用したい人材の特徴を言語化します。求める人物像のニーズも分析が必要です。
・採用人数
どの部署に何人新人を入れるのかを具体的に把握し、退職者の可能性や教育リソース、予算、経営戦略などを考慮して調節しましょう。
・使用する採用媒体
採用活動のなかで、企業情報や採用情報を発信する、SNSや採用メディア、スカウトサービス、採用イベントなどを選定します。発信に際して必要な知識やテクニックもあわせて確認しましょう。
・選考時のルールと評価基準
スムーズに選考が進むように、できるだけ選考時のルールや評価基準を明確化しておきましょう。採用担当者や面接官の主観的な判断で、応募者への評価が決まらないよう注意が必要です。
・内定者フォロー
内定辞退は、企業を悩ませる大きな課題です。新卒者は社会人経験がないため、不安や不信感を抱きやすいため、入社前に信頼関係を築いておく必要があります。
会社説明会の開催
採用計画が固まれば、会社説明会もスムーズに開催できます。新卒採用では、多くの企業の会社説明会が3~4月に実施されます。新卒採用を成功させるには、このタイミングでどれだけの応募者を集められるかがポイントです。母集団(応募者の集合体)が大きくなれば、求める人物像にマッチする人材も集まりやすくなります。できるだけ多くの募集者を集められるよう、自社の魅力や求める人物像、企業風土、待遇などを具体的に紹介しましょう。
書類選考・試験選考・面接選考
会社説明会で集めた応募者の選考を進めます。一般的には、書類選考や試験選考を最初に行い、通過者のみを対象に面接します。「グループディスカッション」「集団面接」「個人面接」と種類があるため、職種ごとに必要な素質を確認できるよう、採用計画を策定しておきましょう。
内定・入社
就活ルールでは、内定出しは10月からとなっているため、9月までに採用を決めた新卒者には内々定を出しましょう。10月になったら内定式を行います。内々定・内定を出しても、応募者は辞退できるため、内定辞退・入社辞退を防止するために、積極的な接触を持つようにしましょう。内定辞退者・入社辞退者を出さないために、ここでも綿密な採用計画が重要となります。
中途採用に関する基礎知識

つづいて、中途採用に関する情報を紹介します。中途採用とは特性も、メリット・デメリットも異なるため、比較しながら確認してください。
中途採用が増加している背景とは
現在、中途採用に力を入れる企業が増えています。新卒採用をメインに採用していた企業のなかには、中途採用の強化にシフトした企業も。現在、中途採用が増える背景には、時代の変化があります。
・働き方の多様化
終身雇用制が崩れ、ワークライフバランスや、多様な価値観が認められるようになったことから、労働者の職場選びや転職に対する意識も変わりました。かつては、「新卒者は、3年は同じ企業で勤務すべき」という定説がありましたが、現在は第二新卒という言葉も生まれるほどに、新卒者でも転職する人が多くなりました。
・ビジネスモデルや業務プロセスの変化
時代の流れとともに、価値観や消費者のニーズも変化しました。現在は時代に沿った新たなビジネスモデルが求められています。さらに、インターネットやIT技術が進歩し、効率的に業務を行うためのプロセスも変わっています。新しいビジネスの形に対応するためには、積極的に新しい知識やノウハウを持った人材を取り入れる必要があるのです。
中途採用のメリット・デメリット
それでは、中途人材を採用するメリット・デメリットはどのようなものなのでしょうか。
メリット①採用後すぐに戦力になる
中途採用では、スキルや経験を絞って募集することができるため、欲しい人材をピンポイントで採用することができます。そのため、長期的に育成する必要がある、優秀なプレイヤーや管理職といった人材も短期間での獲得が可能です。また、未経験者の採用であっても、社会人経験があることから、新卒者のようにゼロからのスタートにはなりません。即戦力性は、中途採用の目的であり、大きなメリットといえるでしょう。
メリット②コストを削減できる
中途採用は、短いスパンで終了します。そのため、長期的なプロジェクトになる新卒採用よりも採用にかかるコストを大きく削減できます。同業他社からの転職者であれば、スキルや経験を持っていることから、自社ならではのルールや業務に関する最低限の研修で業務に入ることができるでしょう。また、未経験であっても、新卒採用のようにビジネスマナーや社会人としての常識から教育するコストは不要です。新卒採用に大きな予算を割り当てられない中小企業やベンチャー企業にとっては、魅力的な特徴でしょう。
メリット③自社にない知識やノウハウを取り入れられる
他社で得た知識や経験といった、業務に関するノウハウを得られる点も中途採用を行うメリットです。同業他社はもちろん、異業種からの転職であっても、自社にはない考え方やアイデア、仕事の進め方が、企業のマンネリ化や業務効率の改善に役立ちます。とくに、新事業を立ち上げたい場合や、業務プロセスを一新したい場合などでは、新しいノウハウを大いに活用できるでしょう。
デメリット①自社に定着せず早期退職もあり得る
転職者の転職理由はさまざまですが、人によっては短期で転職を繰り返す場合があります。そのため、せっかく採用しても、数年で辞めてしまう可能性に留意しなければなりません。転職のハードルが下がり、中途採用が活発化していることからわかるように、自社からの転職者も出やすい環境になっているのです。そのため、早期退職者が出ないよう、採用時には将来のキャリアプランや働き方がマッチしているかをしっかりチェックする必要があります。
デメリット②自分のやり方に固執して組織になじめない
中途採用で採用するのは、他社での経験がある経験者たちです。そのため、自分流のやり方が確立されていたり、これまでのキャリアに対するプライドがあったりする人であれば、自社のやり方や職場になじめない可能性があります。転職者のこれまで培ってきたスキルや、豊富な経験は、自社にとってプラスになることもあれば、マイナスになることもあります。採用時には、柔軟な対応や考え方ができるか、高すぎるプライドを持っていないかなどを確認しましょう。
デメリット③企業がマンネリ化する原因となる
先に触れたとおり、中途採用で同年代の人たちばかり採用し、若手が不足すると、組織の人員バランスがとりにくくなります。そのため企業自体がマンネリ化し、成長がストップする可能性があります。とくに、ミドル世代・シニア世代ばかりの企業であれば、若い世代の新しい考え方やアイデアがなければ、長期的な企業存続は難しくなるでしょう。
中途採用で想定されるターゲットの特徴
一口に中途採用といっても、期待できる能力やキャリアは、世代で異なります。中途採用のターゲットは、「ヤング」「ミドル」「シニア」に大別されるため、それぞれの特徴について確認しておきましょう。中途採用を行うときには、どの世代をターゲットにするのかを明確にし、広く採用したい場合は採用基準を各世代に設けましょう。
<中途採用者の分類>
| 年齢層 | 特徴 | |
| ヤング | 20代 | 「若手」と呼ばれる世代で、最低限のスキル・経験と、将来性の両方を持ち合わせています。 |
| ミドル | 30~50代前半 | 現場のプレイヤーから管理職まで、広く選択肢がある世代です。人によってスキルや経験が大きく異なるため、同じ世代やポジションであっても期待できるポイントには違いがあります。 |
| シニア | 50後半~60代 | 管理職や役員といった、組織運営の中枢を担うポジションを任せられる世代です。退職が目前のため、即戦力性やハイレベルな知識や経験が求められています。 |
中途採用の進め方
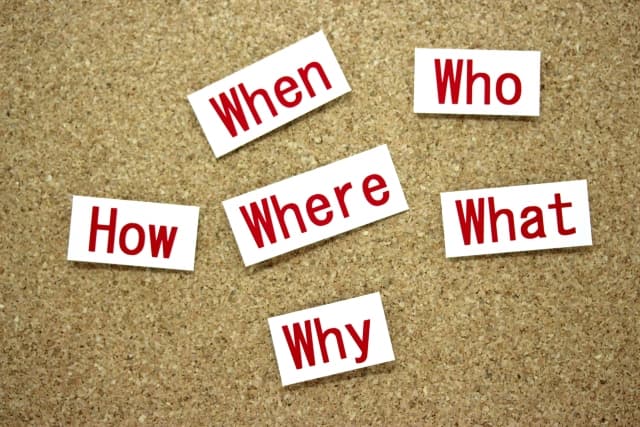
中途採用には、新卒採用のような決まったスケジュールはありません。そのため、必要なタイミングで、迅速に採用を進めることが重要です。
採用計画の策定
採用計画の作成は、中途採用でも活動の第1ステップとなります。考えなければならない内容は大きく変わりませんが、中途採用の場合はターゲットに応じてアプローチを考える必要があります。ターゲットの年齢者や職種ごとに効果的な採用手法や採用媒体は変わるため、求める人物像に合わせて、情報やニーズを収集し、分析・検証しましょう。
書類選考・面接選考
中途採用ではスキルや経験を重視するため、書類選考や個人面接がおもな選考となります。ただし、どのような人物が応募してくるのか完全には読めないため、応募者の要望次第で、給与や待遇、ポジションの変更が必要になる可能性もあります。優秀な人材の確保のために、選考というよりもスカウトに近い形でクロージングするほうが効果的なケースもあるため、柔軟な対応で選考していくのが良いでしょう。
また、中途採用では優秀な経歴を持つ応募者が多くなるため、採用担当者や面接官に求められるレベルも高くなります。担当者への教育にも力を入れましょう。
内定・入社
短い期間で募集から採用まで行う中途採用では、内定の通知から入社までの期間も短い傾向があります。応募者は、他社の選考にも応募している可能性があるため、ほかに流れないようスピード感のあるフローを意識しましょう。前職を退職していない応募者の場合は、スケジュールのすり合わせも重要です。
採用を成功に導くための5つのポイント

新卒採用と中途採用の違いをしっかり確認したところで、どちらの採用活動を行う場合でも覚えておきたい成功のための秘訣を紹介します。採用活動は、一朝一夕で成果が出るわけではありません。長期的な視点を持って、準備を整えて臨みましょう。
採用の目標を明確にする
新卒採用と中途採用どちらに力を入れるか迷っている企業は多いでしょう。その場合は、最初に「なぜ新しい人材が必要なのか」「なぜ採用したいのか」という採用したい目的を明確にしましょう。先に紹介したとおり、新卒採用と中途採用は、採用の目的に大きな違いがあります。まずは、自社に必要な人材が、将来的な戦力なのか、現在の戦力なのかを判断しましょう。
もちろん、コストや社内リソースの問題から、新卒採用が難しい企業もあるでしょう。その場合は、新卒採用を行わないデメリットをカバーできる中途採用を行わなければなりません。
具体的に採用したい人物像を作成する
求める人物像は、できるだけ具体的に詳細まで検討しましょう。求める人物像の明確化には、「ペルソナ」の設計がおすすめです。
ペルソナとは、実在する人物のように年齢や性別、価値観、志向、趣味、生い立ちなど個人的な情報を設定した、架空の採用したい人物を指します。細かく人物像を設定することで、求める人物像のイメージを組織で共有でき、認識のブレも起こりにくくなります。また、価値観や志向、育った環境まで考慮することで、応募者側のニーズの分析や効果的なアプローチを検討することも可能です。
求める人物像にマッチする母集団を形成する
母集団が大きくなる、つまり応募者が増えるほど、選択肢は広がり、優秀な人材が含まれる可能性はアップします。しかし、採用活動を成功させるためには、母集団は大きくなればなるほど良いわけではなく、求める人物像にマッチする応募者による母集団を形成することが重要となります。これは、自社にマッチしない応募者を大量に集めても、採用することができないためです。
求める人物像にマッチする母集団を作れるよう、求める人物像は採用情報を公開する時点で提示しておきましょう。
採用担当者の主観的判断を減らす
採用担当者や面接官の主観的な判断で、採用の合否を決めてしまうと、企業に必要な人材を取りこぼしてしまう可能性があります。
個人的な好き・嫌いや感情を応募者の評価に介入させないようにするためには、客観的な採用基準を設けてリスト化したり、明確な評価ルールの作成が効果的です。また、求める人物像の作成時に、考え方や行動特性を設定しておけば、採用担当者間における共通の基準とすることができます。
採用担当者や面接官のトレーニングを実施する
評価において、主観が入らないようにするためには、採用担当者としてのスキルを磨くことも重要です。採用担当者や面接官のトレーニングには、外部の研修プログラミングを活用すると良いでしょう。また、採用活動中、スムーズに情報を共有し、協力しあえるよう、求める人物像や採用活動の方向性についてしっかりとすり合わせておきましょう。
内定辞退・入社辞退を防ぐためのフォロー

時間をかけて準備し、選考を進めた採用活動も、最後の最後で応募者に断られては意味がありません。内定辞退や入社辞退が発生するおもな原因には、コミュニケーション不足が関係しています。
そこで最後は、内定辞退・入社辞退を防止のコミュニケーション手段として有効なフォローアップを紹介します。
定期的な連絡
内定辞退・入社辞退を防ぐために求められる積極的な接触として、もっとも簡単な方法が、定期的な連絡です。内定者側から事務的な連絡以外を発信することは難しいため、企業側から情報を発信したり、疑問がないか確認したりと積極的に連絡しましょう。内定者との信頼関係構築や、内定ブルーの察知に効果的です。
社内見学の実施
内定直前の応募者をオフィスに招くことで、実際に担当する業務や会社の雰囲気を自分の目で確認してもらうことができます。オフィスツアーとして動画が活用されることもよくありますが、実際の現場を生で見ることで、企業理解が深まるメリットがあります。また、自分が働く姿をイメージできるため、企業と応募者間のミスマッチを防ぐ効果も。内定ブルーになりそうな応募者にとっては、将来一緒に働くかもしれない社員と触れ合いが、安心材料の1つとなるでしょう
将来の上司や先輩社員との懇親会
採用担当者以外の社員と話をする機会も重要です。将来の上司や先輩の人柄を知ることで、内定ブルーやニーズのミスマッチを防止することができます。採用担当者と話すときは、選考中の緊張したシーンが大半なので、カジュアルな雰囲気のなかで疑問や不安を解消できるよう、気軽に質問できる環境を整えることも意識しましょう。
課題の提出
新卒採用の場合、社会人として意識を高めてもらうことも、内定者フォローの一部です。課題を積極的に取り組んでいるか否かで、入社への意欲を計ることができます。また、内定者をグループにして、1つの課題を出すことで、同期同士のコミュニケーションや関係構築をサポートすることが可能です。外部研修などを上手く利用して、定期的に取り組む機会を作ると良いでしょう。
入社前研修・通信教育の実施
インターネットが普及したことで、オンライン研修を容易に実施することができます。とくに、新卒採用の場合社会人として最初に覚える必要がある、心構えやビジネスマナーを入社前から学んでもらうことができます。
研修の内容は、カジュアルなものから厳格なものまで企業によって多種多様です。実施する際は、入社前に会社のことを嫌ってしまわないよう、こまめに成果や不安を確認しながら行いましょう。
メンター制度の導入
内定者1人ひとりを丁寧にフォローするためには、メンター制度を導入するのもおすすめです。メンター制度とは、後輩に、メンター(指導役)の先輩が専属で仕事を教える制度です。同じ部署の先輩がメンターになるため、現場の雰囲気を体感したり、気軽に質問できる環境を作ったりする効果があります。
まとめ
今回は、企業活動のなかでもとくに悩みの多い、採用活動について流れや採用方法の違い、成功させるためのポイントを広く紹介しました。売り手市場の現代でも、計画的に、効果的な採用活動を行えば、自社にマッチする優秀な人材を確保することができます。今回の記事を参考に、ぜひ自社にとってベストな選択を探ってみましょう。
関連記事としてこちらも併せてご覧ください






