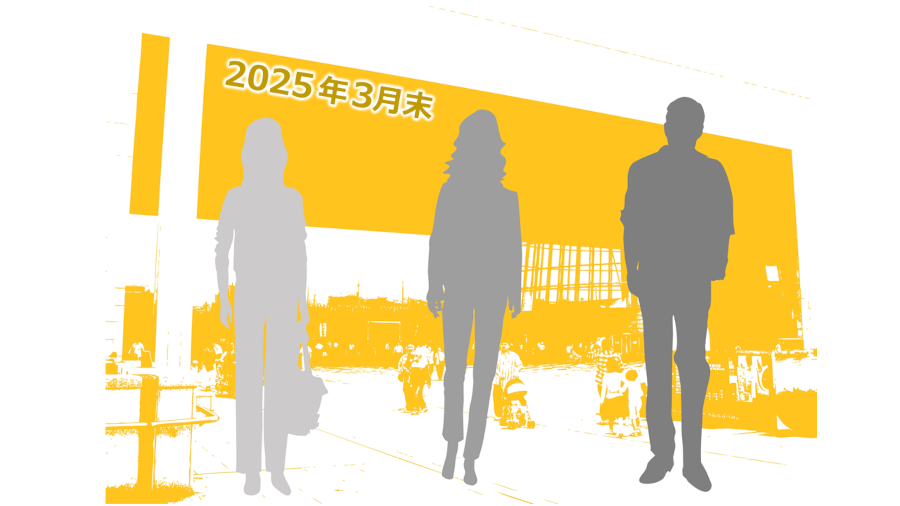公開日:
スタートアップとは?ベンチャー企業との違いや働くメリットを解説

転職活動を進める中で、応募先がスタートアップ企業というケースもあるでしょう。しかし、「スタートアップ」という言葉の意味やベンチャー企業との違いがはっきり分からないという人も多いものです。本記事ではスタートアップ企業の定義やベンチャー企業との違い、さらにスタートアップで働くメリット・デメリットをわかりやすく解説します。スタートアップへの転職を検討している方に役立つ情報を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
スタートアップ企業とは?
スタートアップ企業とは、新しいビジネスモデルや技術を武器に、短期間で急速な成長を目指す企業を指します。もともとはアメリカ・シリコンバレー発祥の言葉で、「開始」や「立ち上げ」を意味する英語 startup に由来しています。
例えば、GoogleやFacebookといった近年の象徴的な米国スタートアップは、革新的な技術とビジネスモデルで急拡大し、短期間で世界的企業へと成長しました。過去に例のないサービスを生み出し、新たな市場を切り開いて急成長する――これがスタートアップの本質と言えるでしょう。
なお日本では、「スタートアップ」という言葉が単に「創業間もない小規模企業」という意味で使われることも多いですが、本来スタートアップかどうかは企業規模や設立年数ではなく、ビジネスの革新性と成長スピードによって定義されます。極端に言えば、創業から年数が経っていても革新的事業で急成長していればスタートアップと呼べますし、逆に新興企業でも従来型ビジネスで緩やかな成長であれば、厳密にはスタートアップとは言いません。
日本におけるスタートアップ企業の特徴
日本でも近年、「スタートアップ」という概念が浸透し、多くの企業が登場しています。ただし、そのビジネス展開には日本独自の傾向も見られます。日本のスタートアップ企業は最先端の技術やアイデアを取り入れつつも、まず国内のローカル市場に特化して成長するケースが多いです。
例えば、2013年創業のメルカリはスマホで手軽に売買できるC2Cマーケットプレイスを提供し、日本国内で急成長した後に海外進出も果たしました。また、2011年創業のクラウドワークスはエンジニアやデザイナーなどフリーランス人材と企業をオンラインで結びつけるサービスを展開し、リモートワークの普及とともに成長しています。これらは日本を代表するスタートアップの成功例であり、いずれも新たな市場ニーズを捉えて急拡大した点が特徴です。
日本のスタートアップでは、大企業との提携や支援を受けながら事業を拡大する例も多く見られます。これは日本のビジネス文化に根ざしたリスク分散の戦略とも言えます。国や文化によって細部は異なるものの、「新しい価値を創造し、革新的なビジネスで急成長を目指す」というスタートアップの本質は共通しています。
日本政府や自治体も近年はスタートアップ支援に力を入れており、補助金や支援プログラムの創設など公的なバックアップも拡充しつつあります。こうした追い風もあり、日本発のスタートアップ企業は年々増加し、経済の活性化に寄与しています。
経営者インタビュー「私の30代」
株式会社クラウドワークス 代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎氏
https://www.pro-bank.co.jp/jobchange/interview30/crowdworks-yoshida/
スタートアップ企業とベンチャー企業の違い
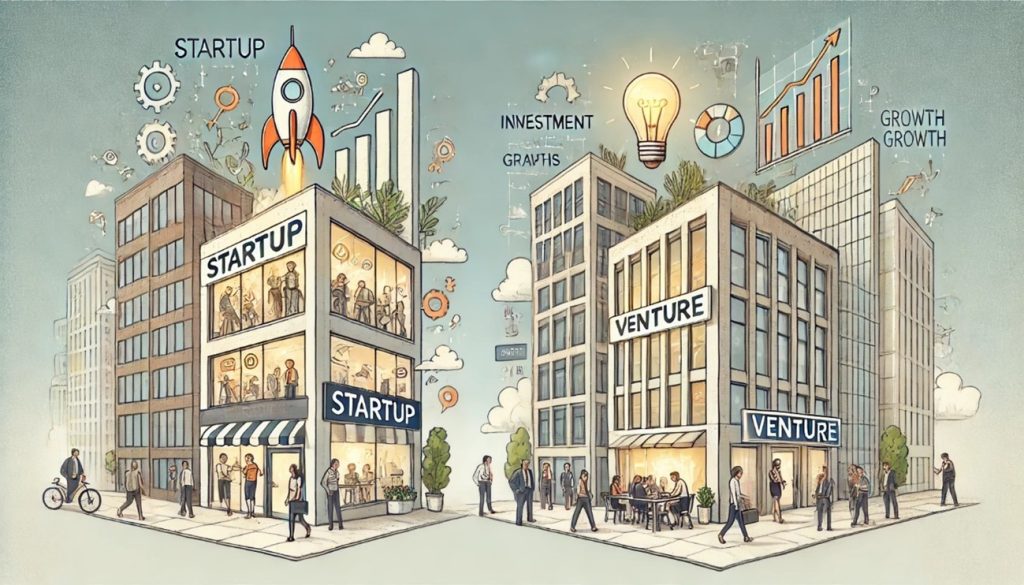
スタートアップ企業とベンチャー企業は、しばしば同義のように扱われますが実際には違いがあります。どちらも「新しいビジネスに挑戦する企業」である点は共通していますし、スタートアップは広義にはベンチャー企業に含まれるとも言えます。しかし、ビジネスモデルの革新性や成長スピード、資金調達の方法、最終的なゴールなどに明確な違いがあります。
ここではスタートアップとベンチャーの違いをポイントごとに解説し、それぞれの特徴を明らかにします。
まずベンチャー企業とは、英語の“venture”が持つ「冒険的な試み」という意味から派生した和製英語で、成長過程にある比較的新しい企業を指す総称です。ベンチャー企業という呼び名自体には厳密な定義があるわけではありませんが、新しいサービスや技術でビジネスを展開する中小企業全般を広く含む概念と言えます。
必ずしも画期的なビジネスモデルでなくても、小規模ながら新規性のある事業に取り組んでいればベンチャーと呼ばれることがあります。つまりスタートアップと比べると、ベンチャー企業という言葉はより幅広い新興企業全般を指すと考えてよいでしょう。
では、スタートアップ固有の特徴は何かを、ベンチャー企業との比較で見ていきます。
ビジネスモデルの違い
スタートアップ企業はゼロから新しい市場や価値を創造する革新的なビジネスモデルを追求します。過去にないサービスや技術を用いてビジネスを構築し、既存の業界に変革をもたらすことを目指します。
例えば、UberやAirbnbは従来のタクシー業界やホテル業界に対して全く新しい仕組み(ライドシェアや民泊プラットフォーム)を導入し、業界構造そのものを変えてしまいました。スタートアップはこのように大きなリスクを取ってでも独自のビジネスモデルを生み出す点が特徴です。
一方でベンチャー企業は、必ずしもビジネスモデル自体が革新的とは限りません。既存のビジネスモデルや成功事例をベースにしつつ、新しい市場に参入したりユニークな付加価値を加えたりして事業拡大を図るケースが多いです。
例えば、フランチャイズ展開で地域を拡大する飲食チェーンや、既存製品に改良を加えて市場シェアを奪うような企業も広い意味でベンチャーに含まれます。つまりベンチャー企業は、スタートアップほどの大胆な革新性や不確実性を伴わず、比較的オーソドックスなビジネスの延長線上で成長を目指す傾向があります。
成長スピードの違い
スタートアップ企業は短期間での急成長、いわゆるハイペースなスケールアップを重視します。市場で早期に圧倒的シェアを獲得することを狙い、組織や事業を急拡大させます。例えば、Instagramは創業からわずか2年程度でユーザー数を伸ばし、2012年にFacebookに買収されるほどの規模に成長しました。このようにスタートアップはとにかくスピード重視で事業を展開し、短期間で大きな成果を追求します。
それに対してベンチャー企業は、スタートアップほど成長のスピードを求めません。持続的で堅実な成長を目標とし、安定した収益基盤を築きながら段階的に事業規模を拡大していく傾向があります。市場参入も一気呵成に拡大するのではなく、綿密な市場調査を経て少しずつ展開するなど、リスクを抑えつつ成長するのが一般的です。
つまり成長曲線で言えば、スタートアップが急激なJカーブを描くのに対し、ベンチャー企業は右肩上がりの緩やかなカーブを描くイメージです。
資金調達と収益モデルの違い
スタートアップ企業は、ビジネスモデルが軌道に乗るまで赤字覚悟で先行投資するケースが多く、創業当初から数年間は収益が安定しないこともしばしばです。そのため、必要な事業資金をまかなうためにベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などから積極的に外部資金を調達します。いわば将来の成長を見越して投資を受け、当面の収益性よりも事業拡大を優先するのがスタートアップの戦略です。
こうした初期段階の資金繰りの厳しさは「死の谷(Valley of Death)」とも呼ばれ、多くのスタートアップが直面する壁でもあります。しかしこの谷を乗り越えて新たな価値を生み出せれば、短期間での飛躍的成長と将来的な高収益が期待できます。
一方ベンチャー企業は、事業モデルが比較的定型化されている分、早期から一定の収益が見込めることも多く、スタートアップほど大量の資金調達に依存しない傾向があります。自己資金や銀行借入、助成金などで必要資金を賄い、まずは黒字化・安定経営を目指しながら徐々に規模拡大していくのが典型です。
昨今ではスタートアップ支援策として国や自治体からの補助金、助成金制度も充実してきていますが、こうした公的支援は特に革新的なスタートアップに手厚くなっており、従来型の中小企業(ベンチャー)は主に金融機関からの融資などオーソドックスな方法で資金を調達することが多いでしょう。
ゴール(Exit)の違い
スタートアップ企業は最終的なExit(出口戦略)を明確に描いていることが多いです。創業から短期間で事業価値を高めた後、IPO(新規株式公開)やM&Aによる売却といった形で大きなリターンを得ることを目標にします。
例えば、ビジネスチャットツールで急成長したSlackはわずか数年で株式上場を果たし、その後2021年にSalesforce社に巨額で買収されました。このように、スタートアップの創業者や初期投資家は株式売却によるキャピタルゲインを大きなゴールの一つとしています。
一方ベンチャー企業は、必ずしも明確なExitを追い求めません。長期的に事業を継続・成長させること自体が目的であり、創業者がそのまま経営を続けたり、次世代に事業承継して中堅企業へと成長していったりするシナリオも一般的です。
例えば、オーナー家が経営する老舗企業が新規事業に挑戦して徐々に規模拡大している場合など、外部への売却や上場よりも事業の安定と永続を重視します。もちろん状況によってはIPOやM&Aを選択することもありますが、それはあくまで成長過程での選択肢の一つにすぎず、必須のゴールではありません。
要するにスタートアップは「短期勝負で価値を最大化しExitする」志向が強く、ベンチャー企業は「長く事業を続け安定成長させる」志向が強いと言えます。それゆえ、スタートアップの経営陣や投資家はExitまでの具体的なロードマップを描いて動く一方、ベンチャー企業は無理にExitを急がず足元の収益拡大や市場での地位確立に重きを置く傾向があります。
スタートアップ企業で働くメリット

ここまでスタートアップ企業の特徴を見てきましたが、実際にそこで働くことにはどのような魅力があるのでしょうか。スタートアップ企業はその革新性と成長スピードゆえに、働き手にとっても大きなチャンスを提供してくれます。特に新しいことに挑戦したい人や、自身の成長スピードを加速させたい人にとって、スタートアップは非常に魅力的な職場となりえます。主なメリットを順に見ていきましょう。
成長機会が豊富で急速に学べる
スタートアップ企業で働く最大のメリットの一つは、成長と学習の機会が非常に豊富なことです。常に新しいアイデアや技術に挑戦する環境のため、社員は最新の業界動向やスキルに触れながら仕事を進めていきます。
大企業では分業化されている業務も、スタートアップでは一人ひとりの役割範囲が広く、複数の業務領域にまたがって経験を積むことができます。意思決定のスピードも速く、次々と新しい課題に取り組むため、短期間で濃密な実務経験を得られるでしょう。こうした環境下では、自身の市場価値となるスキルセットを通常より早いペースで磨き上げ、キャリアを大きく前進させることが可能です。
自分の意見や創造性が仕事に直結する
スタートアップでは組織規模が小さい分、各メンバーの存在感が大きく、自分の意見やアイデアを仕事に反映させやすいというメリットがあります。大企業では通りづらい斬新な提案でも、スタートアップならば即座に採用されプロジェクトに組み込まれることも珍しくありません。役職や年次に関係なくフラットに意見交換できる文化を持つ企業も多く、若手であっても経営に近い立場で仕事を進める機会があります。
自ら考えたアイデアがサービスや製品として形になり、事業の成長に結びつくのを実感できるのは、大きなやりがいです。また既存の常識にとらわれない自由な発想で仕事ができる風土があるため、クリエイティブなアプローチを存分に試し、自分の創造性をビジネスに活かせる点も魅力でしょう。
働き方が柔軟で成功すれば大きなリターンも
スタートアップ企業の多くは柔軟な働き方を取り入れています。リモートワークやフレックスタイム制度、副業OKなど、大企業では難しい働き方も比較的受け入れられやすく、個人の裁量で効率よく働ける環境が整っていることがあります。少人数ゆえのフットワークの軽さから、制度面でも新しい取り組みに積極的な企業が多いのです。
さらに、スタートアップは創業期こそ大企業より給与水準が低めの場合もありますが、成功した際のリターン(報酬のポテンシャル)が非常に大きい点も見逃せません。ストックオプション(自社株購入権)や業績連動のインセンティブが付与されるケースが多く、会社の成長とともにそれらの価値が跳ね上がれば、将来的に大きな収入を得るチャンスがあります。「目先の安定収入より将来の大きな成果に賭けたい」という人にとって、スタートアップは夢のあるフィールドと言えるでしょう。
スタートアップ企業で働くデメリット
魅力の多いスタートアップでの仕事ですが、一方で覚悟しておくべきデメリットや大変な点も存在します。急成長や革新を目指す環境は、その分だけ負荷やリスクも大きいものです。スタートアップへの転職を考える際は、メリットだけでなくデメリットもしっかり理解した上で、自身に向いている働き方かどうか判断することが重要です。ここではスタートアップ企業で働く主なデメリットを見ていきましょう。
労働負荷が高くハードワークになりやすい
スタートアップ企業では仕事量やプレッシャーが大きく、長時間労働になりがちです。新しいアイデアや製品を競合よりも早く市場に出す必要があるため、プロジェクトの進行は常にスピード勝負。納期前には深夜残業や徹夜作業が避けられない場面もあります。
また人手が限られている分、一人ひとりが担う役割が多岐にわたりがちです。専門外のタスクにも臨機応変に対応しなければならず、複数の仕事を掛け持ちすることで常に手一杯…という状況も珍しくありません。
近年は働き方改革でスタートアップでもリモート勤務やフレックスを導入する例はありますが、それでも仕事量自体の多さからワークライフバランスの確保が難しい場合もあります。加えて、社内の仕組みやルールが未整備な部分も多いため、自分たちでゼロから環境を作り上げていく負担も生じます。こうしたハードワークに対応できないと、スタートアップで働き続けることは難しいでしょう。
収入が不安定で経済的リスクがある
もう一つの大きなデメリットは、収入面の不安定さです。前述の通りスタートアップは事業初期には赤字が続くことも多く、会社の資金繰りや業績は変動しやすいものです。その影響は従業員の給与や待遇にも及びます。状況によっては給料の支払いが遅れたり、一時的に減額を余儀なくされたりするリスクもゼロではありません(極端な場合、倒産すれば給与未払いという最悪の事態もありえます)。
また、一般にスタートアップの基本給は大企業より低めに設定されることが多いです。その代わりとして、ストックオプションなど将来の成果報酬が用意されるわけですが、もちろんそれが実際に利益につながる保証はありません。もし会社が成功しなかった場合、株式の価値はゼロになってしまいます。
結果として勤めた期間の収入が抑えられ、貯蓄や生活設計に狂いが生じるリスクは考慮しておかなければなりません。安定した固定収入を第一に考える人にとって、スタートアップ勤務は経済的に不安の大きい選択肢と言えます。
会社存続やキャリアの先行きが不透明
スタートアップ企業は常に倒産や事業撤退のリスクと隣り合わせです。新規ビジネスが成功する確率は決して高くなく、多くのスタートアップが数年以内に撤退を余儀なくされるとも言われます。市場環境の変化や競合の出現、資金調達の失敗など、様々な要因で事業計画が崩れ、会社自体がなくなってしまう可能性もあります。当然、自分のキャリアも計画通りにいかなくなる恐れがあります。
仮に会社が順調に成長してめでたくExit(IPOやM&A)を迎えた後であっても、その後に環境が大きく変わるケースが多々あります。上場すれば組織が拡大しルールも整備されて社風が変わるかもしれませんし、他社に買収された場合は親会社の方針で部署再編や人員整理が行われる可能性もあります。創業メンバーとして頑張ってきたポジションが突然変わったり、新しい経営陣の下でやりたいことができなくなったりするケースも考えられます。
このように、スタートアップでのキャリアは先行きが読みにくく不確実性が高いことを十分認識しておく必要があります。
スタートアップ企業で働くのに向いている人

ここまでメリット・デメリットを挙げましたが、実際問題としてスタートアップで働くことに向き・不向きはあります。ではどのような人がスタートアップにフィットしやすいのか、主な適性や共通点を整理してみましょう。以下のような特性に当てはまる方は、スタートアップで力を発揮しやすく、充実したキャリアを築ける可能性が高いと言えます。
変化に柔軟に適応できる
まず、環境の変化に柔軟に対応できる人はスタートアップ向きです。スタートアップ企業は事業の成長過程で目まぐるしく状況が変化します。組織体制や方針が次々にアップデートされる中で、その都度スピーディーに順応していかなければなりません。むしろ変化を楽しめるくらいの方が望ましいでしょう。
逆に安定した環境で決まった業務を着実にこなしたいタイプの人には、毎日が変化の連続であるスタートアップはストレスフルに感じられるかもしれません。
自主性が高く自己管理できる
主体的に動ける人、自走できる人もスタートアップでは歓迎されます。少人数の組織では一人ひとりが担う責任範囲が大きく、指示を待つのではなく自分で考えて仕事を進める必要があります。新人だからといって手厚い研修やマニュアルが用意されているとは限らず、いきなり実践投入されることも珍しくありません。
そうした中でもしっかり自己管理し、自分で学びながら成果を出していける人でなければ務まらないでしょう。「与えられた仕事をやる」という受け身ではなく、「自分で仕事を作りにいく」くらいの自主性がある人ほどスタートアップでは活躍できます。
課題解決が得意で創意工夫が好き
スタートアップでは常に新しい課題に直面するため、高い問題解決能力が求められます。前例のない問題でも粘り強く考え抜き、解決策をひねり出せる人が重宝されます。また、仕組みが整っていないことが多い分、自分たちで試行錯誤しながら改善していく場面も多くなります。
そうした創意工夫の余地を前向きに捉え、「どうすればもっと良くできるか」とクリエイティブに発想できる人に向いています。反対に、与えられたフォーマット通りに動く方が安心できるというタイプだと、未知の問題に対応するプレッシャーが大きく感じられるでしょう。
コミュニケーション能力が高い
チームが小さい分、メンバー同士の緊密な連携がスタートアップ成功の鍵となります。そのため、円滑なコミュニケーション能力は非常に重要です。自分の意見を適切に伝える力はもちろん、チームメンバーや関係者との情報共有・調整をスムーズに行えることが求められます。
スタートアップでは部署の垣根も低く、エンジニア・営業・デザイナーなど職種を超えて協働する機会が多々あります。そうした多様なバックグラウンドの人々とオープンに議論し協力できる柔軟なコミュニケーションスキルを持つ人は、とても頼りにされるでしょう。
リスクを恐れず粘り強い
高いリスク耐性と粘り強さを持つ人もスタートアップ向きです。前述のようにスタートアップには不確実な要素や困難がつきものです。計画通りにいかないことも多く、何度も壁にぶつかる覚悟が必要です。それでも簡単に諦めず、失敗から学んで次に活かす前向きさや精神的タフさを持っている人が活躍します。
「失敗したらどうしよう」と尻込みするより「失敗してもそこから這い上がればいい」というくらいの肝の据わった人材こそ、スタートアップには不可欠です。
将来起業を目指している
最後に、スタートアップでの経験は将来自分で起業したい人にも大いに役立ちます。実際、将来の起業準備としてあえてスタートアップ企業に飛び込む人も少なくありません。スタートアップでは経営者との距離が近く、会社の成長プロセスを間近で見られるため、ビジネス立ち上げのノウハウやマインドセットを学ぶことができます。
また、自ら新規事業を生み出す一連の流れを体感できるので、将来独立する際の貴重な糧となるでしょう。もし「いつか自分の会社を持ちたい」という起業志向があるなら、スタートアップで働くことは最高の実地トレーニングと言えます。
スタートアップ企業を選ぶ際のポイント
スタートアップへの転職を考える際には、どの会社を選ぶかも非常に重要です。一口にスタートアップと言っても、事業内容や成長段階、社風などは千差万別です。自分に合ったスタートアップ企業を見極めるために、以下のポイントに注目してみましょう。
企業の理念やビジョンに共感できるか
まずはそのスタートアップ企業が掲げる理念やビジョンに共感できるかどうかを確認しましょう。スタートアップで働く上では、目まぐるしい日々の中でも「この事業を成功させたい」という強いモチベーションが支えになります。その源泉となるのが会社のミッションやビジョンです。
自分が価値を感じられる理念を持った企業であれば、困難な局面でもやりがいや意義を見出しやすく、前向きに頑張れるでしょう。
事業内容や市場に将来性があるか
次に、そのスタートアップの事業内容や狙っている市場に成長性があるかを見極めることも大切です。スタートアップは不確実性が高いからこそ、伸びる市場で勝負しているかどうかで成功確率が大きく変わります。
例えば、AI・ブロックチェーン・バイオテクノロジーなど革新的で成長著しい分野に挑戦している企業は、順調にいけば事業拡大の恩恵を受けやすいでしょう。逆に市場自体が頭打ちだと感じられるビジネスだと、いくら頑張っても限界があるかもしれません。応募前に業界動向を調べ、その会社のサービスやプロダクトに将来性を感じられるか考えてみてください。
経営陣やチームメンバーに魅力があるか
一緒に働く人も重要なチェックポイントです。スタートアップでは特に経営陣との距離が近いため、創業メンバーの人柄や能力、ビジョンに共感できるかはモチベーションに直結します。経営層が魅力的で信頼できる人物かどうか、面接などを通じて感じ取ってみましょう。
また現在働いている社員の雰囲気や価値観も、自分に合うかどうか大切です。組織がフラットでスピード感を重視する文化なのか、若手でも裁量を持てる環境か、といった点も確認できると安心です。自分がそのチームの一員として最大限力を発揮できそうかイメージしながら企業研究をすると良いでしょう。
資金調達状況や待遇面の条件はどうか
スタートアップ企業の資金力や財務状況も無視できません。しっかり資金調達できている企業は、投資家から期待と評価を得ている証拠でもあり、事業継続性の面でも一定の安心感があります。公式発表やニュースリリースで資金調達の有無や規模をチェックしたり、上場企業であれば財務データを確認したりしましょう。また、提示される給与やストックオプションの条件も現実的に重要です。
スタートアップは将来性重視とはいえ、生活に直結する待遇があまりに許容範囲外だと長くは続きません。リスクある環境に飛び込む以上、見返りとして期待できるストックオプションやボーナスの制度についても十分納得した上で入社を決断しましょう。
以上のポイントを踏まえつつ、自分にとって譲れない条件や優先順位を明確にすると、数あるスタートアップ企業の中から納得のいく転職先を見つけやすくなります。
まとめ
スタートアップ企業は、革新的なビジネスで急成長を目指すダイナミックな職場です。そこでは大企業では得られない成長と学習の機会、創造性を発揮できる環境、柔軟な働き方や将来的な高リターンの可能性など、多くの魅力的なメリットがあります。一方で、激務になりやすい労働環境や収入の不安定さ、会社の存続リスクといったデメリットも存在します。
スタートアップへの転職を成功させるには、これらメリット・デメリットを正しく理解した上で、自分の志向やライフスタイルに合っているかを見極めることが大切です。また、企業ごとの理念・事業の将来性・チーム・資金状況などを調べ、自分にフィットするスタートアップを選ぶことも大きなポイントになります。
もし本記事を読んで、スタートアップ企業で働くことに魅力を感じ「チャレンジしてみたい!」と思われた方は、ぜひ行動に移してみましょう。
プロフェッショナルバンクは人材紹介会社として、スタートアップ企業のハイクラス求人も多数扱っております。スタートアップ転職を検討する中で不安な点や知りたいことがあれば、ご登録のうえお気軽にご相談ください。あなたの新たな一歩を専門のキャリアコンサルタントがしっかりサポートいたします。ぜひスタートアップの世界に飛び込み、これまでにない経験と成長を手に入れてください。