パワハラとは?パワハラ防止法が定める定義・種類・判断基準を紹介/対処法も解説

何をもってパワハラか。社員から相談を受けたときに、パワハラの定義を理解したうえで対応できているでしょうか。
本記事では、法的観点から見たパワハラの判断基準を紹介し、パワハラが起きてしまった現場への対処法を解説します。最後には事例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
目次
パワハラとは?
パワハラとは、立場の優位性を利用した、労働者に対する嫌がらせ行為や苦痛を与える行為のことを指します。正式名称はパワーハラスメントであり、権力(パワー)による嫌がらせ(ハラスメント)という意味です。パワハラの定義は、厚生労働省が下記のように定めています。
職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
厚生労働省が定めるパワハラの種類
本章では、厚生労働省が定義するパワハラの種類について深掘りしていきます。
パワハラの種類(6類型)
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
①身体的な攻撃
暴力を振るうことで、受け手側の労働者を力で支配しようとするパワハラの類型です。殴る、蹴る、押す、物を投げる等の接触を伴い危害を与える行為が代表的です。
②精神的な攻撃
侮辱したり、人格を否定したり、受け手側の労働者に精神的な苦痛を与えるパワハラの類型です。暴言を吐く、威圧的な態度をとる、大勢の前で叱る、大勢を宛先に入れたメールで暴言を吐く、十分な指導をせずに放置する等の行為が挙げられます。
③人間関係からの切り離し
受け手側の労働者を仲間外れにすることで、良好な人間関係を築けなくする嫌がらせ行為です。仕事を与えない、会議から外す、挨拶を無視する等の会社に居づらい環境を作り出す行為が該当します。
④過大な要求
明らかに達成不可能な業務を受け手側の労働者に強要する行為もパワハラです。英語が苦手な社員を海外転勤させる、指導もせずに経験のない業務に就かせる、意に反して休日出勤させる等の過酷な環境を作り出す行為が当てはまります。
⑤過小な要求
逆に、受け手側の労働者の能力を遥かに下回る業務のみ与え続ける行為もパワハラです。営業職の社員に掃除の役割しか与えない、1日中お茶汲みしかさせない等の、受け手の労働者に会社への貢献度が希薄であると感じさせてしまう行為を指します。
⑥個の侵害
受け手側の労働者のプライベート領域に対して過剰に踏み入れる行為もパワハラです。飲み会にしつこく誘う、休暇の理由を執拗に聞く、私物の写真を撮影する、パートナーや配偶者との関係を詮索する等のプライバシーを侵害する行為が該当します。
パワハラ防止法が定める判断基準
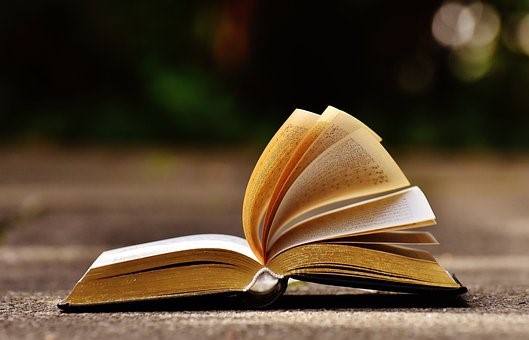
パワハラ防止法とは?
パワハラ防止法とは、企業側にパワーハラスメント防止のための必要な措置を義務付けた法律です。「改正労働施策総合推進法」とも呼ばれ、大企業は2020年6月1日から、中小企業は2022年4月1日から施行されました。
パワハラの判断基準(3要素)
パワハラ防止法では、パワハラの判断基準として3つの要素を挙げています。この3つの要素を“全て”満たすものが、パワハラに該当するということになります。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③労働者の就業環境が害される
①優越的な関係を背景とした言動
行為の受け手側である労働者が、行為者に対して「断る」「抵抗する」という意思表示ができない可能性がある関係性で行われることは、パワハラの要素の1つです。受け手側が一方的に圧力をかけられる構図であり、健全な関係性とは言えません。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
一般常識に照らし、明らかに業務の目的を逸脱した行為や業務を遂行する手段として不適切な言動が見受けられるとパワハラ要素の対象になります。例えば、個人的な要求のための命令やミスに対する土下座の強要などが挙げられます。
③労働者の就業環境が害される
行為の受け手側である労働者が、身体的もしくは精神的に苦痛を感じ、職場環境が不快なものとなったために、能力の発揮に重大な悪影響が生じるといった業務上許容できない程度の支障をきたす行為もパワハラの要素です。ミスに対する暴言や暴力、強い口調での会話、無視や冷遇など、身体的・精神的な苦痛は通常の業務遂行を阻害する要因になります。
<参照>【北海道労働局】労働施策総合推進法(パワハラ防止対策義務化)説明資料
パワハラが起きた現場への対処法
ここからは、実際にパワハラが起きてしまった現場に対する適切な対処法を紹介します。パワハラを受けた社員とパワハラをした社員、そしてパワハラが起こった部署に対する会社の対応を解説していきます。
1. パワハラを受けた社員へのフォロー
主治医とのカウンセリング面談
最優先で対応するべき対処が、パワハラを受けた社員へのケアです。メンタルヘルスの不調が深刻になると職場復帰に時間がかかってしまいます。パワハラ相談があったときに部署内だけで解決を図ろうとするのは困難です。主治医と連携してカウンセリングを実施し、パワハラを受けた社員の心理的サポートを第一に実施することが大切です。
事実関係の調査
次に事実関係の調査として、パワハラの内容・頻度・言動・対象者などをヒアリングします。主治医とのカウンセリングを実施することでパワハラを受けた社員の心理状態に配慮しながら、事実関係の調査を進めていく必要があります。
解決策の提示
パワハラを受けた社員の気持ちを可能な限り受け入れて、今後の働き方や職場復帰への期間・業務内容をしっかりと話し合い、再び就業できる職場環境を明示しましょう。
2. パワハラをした社員への対応
事実関係の調査
パワハラをした社員はハラッサーと呼ばれます。会社の対応として、ハラッサーにも事実関係を調査することが適切です。ハラッサーのほとんどが、パワハラの受け手に与えた自身の行為についてパワハラであるという自覚はありません。そのため、ハラッサー側の主張もヒアリングしたうえで調査を進め、場合によっては行動変容を促すサポートを講じる必要があります。
専門家による行動変容サポート
ハラッサーに対しては、自身の行動がパワハラに該当する行為であると自覚してもらうことが第一です。ハラッサーに問題行動だけ改善してくれれば、成果と能力は維持してほしいと思う企業も実際にあります。しかし、人事異動や組織再編を簡単に実施するわけにもいかず、外部専門家による行動変容サポートを活用して再発の防止に努めましょう。
定期面談
定期的に面談を実施し、行動の変容を確認します。その際には、どのような行為がパワハラに該当するのか、どのような点を注意してマネジメントしてほしいかを明確に伝えていきましょう。
また、定期面談の議事録を取っておくことを推奨します。ハラッサーに改善が見られないケースもあり、配置転換を余儀なくされることもあるでしょう。不当な強制があったと訴えられた場合も、会社として適切な対応は取ったうえでの配置転換であることを証明することができます。
懲戒処分が必要と判断する際には、定期面談の内容も含めて処分の内容を決定していくため、処分の判断材料として記録を残しておくことが重要です。
3. パワハラが起こった部署の措置
事実関係の調査
公平な調査となるよう、パワハラを受けた社員とパワハラをした社員に加えて、第三者目線での事実関係の確認を実施する必要があります。当事者間の主張だけに留まらず、客観的に見てパワハラに該当しているか否かを見極めるための重要な対応になります。
定期的なストレスチェック
次に、パワハラが起きた部署のメンバーにストレスチェックを実施しましょう。パワハラを相談した社員の他にも、パワハラによるストレスを言えずに抱え込んでいる社員がいるかもしれません。また、自身がパワハラを受けていなくても、パワハラが横行する職場にいて気分が良いものではありません。
定期的にストレスチェックを実施することで、部署のメンバーの些細な気持ちの変化にも配慮できるようにしましょう。
相談窓口の設置
最後に、再発防止のために相談窓口を設置します。「パワハラが発生したことを報告する窓口」ではなく、「パワハラに限らず業務における広い相談窓口」と設定することで、職場環境悪化の早期発見に繋がり、パワハラ化する前の予防策になる効果があります。
パワハラの判断が難しい事例
マネジメントをしていると、部下の行動に対して注意喚起したり、必要な業務を任せたり、様々なコミュニケーションを取る機会があります。その度にパワハラに当たるのではないかと怯えていては、スムーズな業務遂行に支障をきたしてしまいます。

本章では、パワハラに該当するかどうかのグレーゾーンな事例に対して、パワハラ防止法の定める3つの要素と照らし合わせて、パワハラか否かを判断します。
※パワハラの基準(3要素)を“全て”満たしている行為がパワハラに該当します。
【事例1】部下への注意・指導
遅刻や服装の乱れ、髪型の規程違反が目立つAさんに対して、幾度となる注意喚起をするも改善が見られない。そのため、Aさんに対して強く注意した。
| パワハラの基準(3要素) | 判断 |
| ①優越的な関係を背景とした言動 | ○ |
| ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 | ✖ |
| ③労働者の就業環境が害される | ✖ |
この場合、上司は業務上必要かつ相当な範囲内での言動であること、また、Aさんの就業態度を改善するための言動であり、就業環境を害するものではないため、パワハラには該当しない事例です。
しかし、暴力を振るって従わせる行為が伴うと②③の要素を満たすことになります。社員の就業態度に問題がある場合でも、上司という優越的な立場にいる以上、“身体的な攻撃”による支配は控えましょう。
【事例2】自分の指示を聞くように別室での業務を強要
BさんとCさんを部下に持ち、事業を推進している。Bさんは指示したことに対して忠実に業務を遂行してくれるが、Cさんは指示に対して意見をしたり、提案をしたり、思い通りに動いてくれない。そのため、長期間にわたり別室に隔離して業務をさせ、自分の意に沿うように誘導した。
| パワハラの基準(3要素) | 判断 |
| ①優越的な関係を背景とした言動 | ○ |
| ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 | ○ |
| ③労働者の就業環境が害される | ○ |
この場合、全てのパワハラ基準を満たしているため、パワハラに該当する事例です。優越的な立場を利用した言動であり、長期間の別室隔離での業務指示は業務上必要かつ相当な範囲を超えており、メンバーとの交流が阻害される点は就業環境を害する要因になると言えるでしょう。
今回の事例は、人間関係の切り離しというパワハラ類型に該当します。また、隔離はしなくとも、自分の意に沿わない社員に対して仕事を依頼しない行為も過小な要求としてパワハラに該当してしまいます。部下とのコミュニケーションの取り方や仕事の依頼方法など、指導方法がエスカレートしてパワハラに該当する行為をすることは控えましょう。
【事例3】社員の育成のためにハイレベルな業務を依頼
通常の業務を淡々とこなし、仕事のスピードも速いDさん。上司はDさんのスキル向上を目的に、当面の業務負担が増えることを本人に伝えたうえで現状よりも少し高いレベルの業務を任せた。
| パワハラの基準(3要素) | 判断 |
| ①優越的な関係を背景とした言動 | ○ |
| ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 | ✖ |
| ③労働者の就業環境が害される | ○ |
この場合、上司から部下へ業務負担を増やしている行為のため①③に該当しますが、Dさんの育成を目的とした指示であり、業務上必要かつ相当な範囲内の言動であると言えます。そのため、パワハラには該当しません。
仕事に関係のない依頼や自分の仕事を押し付ける行為は、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とみなされるため、②に該当しパワハラの対象となります。過大な要求にならないためにも、社員の経験とスキルを鑑みた適切な育成ができるような仕事を依頼しましょう。また、仕事を任せる際は、その目的を明確に伝えることで部下もモチベーション高く業務を遂行することができます。
まとめ
今回はパワハラに関する法的知識から事例まで解説してきました。パワハラの判断基準と種類を知っておくだけで、予防対策と発生時の対処法を実行に移せるでしょう。勤務体系に縛りがなくなったこの時代、常に社員が働きやすい環境を維持するために、パワハラに関する知識は持っていて損はありません。
関連記事としてこちらも併せてご覧ください






